半纏(はんてん)とどてらは、どちらも冬に着る防寒用の和服ですが、いくつかの違いがあります。
半纏

「はんてん」とは、江戸時代に庶民の間で着用されていた防寒着のことです。
はんてんの元々の由来は、袖が半分という所から「半丁(はんてん)」と呼ばれていて、そこに「纏う」という意味がプラスされて半纏(はんてん)と書かれるようになったそうです。
その特徴は、羽織に近い形状で、表地と裏地の袷(あわせ)であること。
また、綿が入っているものもあり、袖丈は五分くらいです。大工さんなどの作業着や、時代劇などで目にすることもある火消しのユニフォームとしても利用されています。
- 主に家庭内で着用される防寒着
- 丈は短く、腰のあたりまで
- 袖は短く、筒袖(つつそで)と呼ばれる形が多い
- 中綿が入っているが、どてらほど厚くはない
- 衿は折り返さない
リンク
どてら

「どてら」とは、旅館などで冬場の湯上りに和服の上から着用していた防寒着のことです。
「どてら」は、羽織りやすいように通常の着物よりも大きめに作られており、綿が入っているのが特徴です。
別名「丹前(たんぜん)」とも呼ばれ、江戸時代に流行した「丹前風呂」が由来となっています。
- 外出用としても着用される防寒着
- 丈は長く、膝下まであるものもある
- 袖は長く、袂(たもと)と呼ばれるふくらみがある
- 中綿がたっぷり入っており、保温性が高い
- 衿は折り返すことができる
リンク
その他
- 素材:半纏は綿やウール、どてらは綿や絹などが使われることが多い
- 柄:半纏はシンプルな柄が多いが、どてらは華やかな柄のものもある
- 用途:半纏は部屋着やちょっとした外出に、どてらは寒い日の外出や旅行などに使われる
さいごに
どちらを選ぶかは、用途や好みに合わせて決めるのがおすすめです。
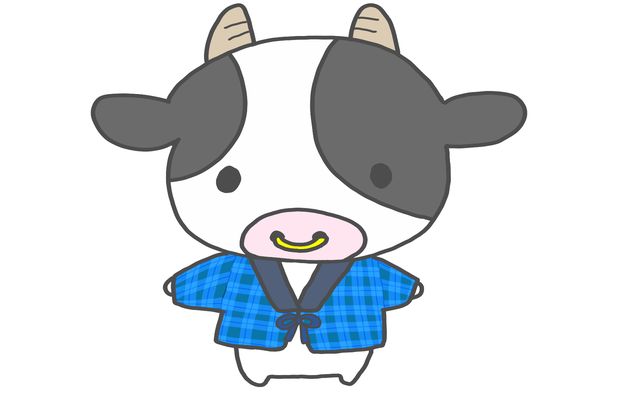
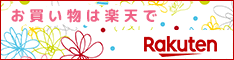


コメント