**「お米(ご飯)は太るから食べない方がいい!」**という話をよく聞きませんか?
糖質制限ダイエットが流行する中で、大好きなお米を我慢している人も多いかもしれません。
でも、ちょっと待ってください!お米って本当に太る「悪者」なんでしょうか?
今日は、この「米は太る」説の真相を、科学的な根拠も交えて徹底解説します!
結論!「お米は太る」は大きな誤解です!
いきなりですが、結論から言います。
「お米は太る」というのは、実は大きな誤解です!お米が直接的に体重増加の原因になるわけではありません。
誤解の根源は「カロリー収支」と「糖質」
なぜ、「お米は太る」という説が広まってしまったのでしょうか?主な原因は次の2つです。
- カロリーオーバーが原因なのに、お米だけを悪者にしている どんな食品でも、**「摂取エネルギー(カロリー)が消費エネルギーを上回る」**状態が続けば、余ったエネルギーは体脂肪として蓄積され、太ります。お米も例外ではありませんが、これはお米に限った話ではありません。
- 糖質=悪、という極端な認識 お米の主成分は「炭水化物」(糖質+食物繊維)。この糖質が「太る原因」とされがちですが、糖質は脳や体を動かすための重要なエネルギー源です。糖質を極端にカットすると、集中力の低下や疲労感につながる可能性があります。
科学的に見る!お米が「太りにくい」理由
では、お米にはどんなメリットがあり、なぜ太りにくいと言えるのでしょうか?
1. 脂質が圧倒的に少ない!
お米は、パンや麺類といった他の主食と比べても、脂質が非常に少ないのが特徴です。
- 脂質は、炭水化物やタンパク質に比べて、1gあたりのカロリーが約2倍(9kcal)もあります。
- お米は、水だけで炊くため、調理過程で余分な脂質が加わることがありません。これが、脂質過多になりがちな現代の食生活において、バランスを保つ上で大きなメリットとなります。
2. 腹持ちが良く、食べ過ぎを防ぎやすい
お米は粒状で、よく噛んでゆっくり食べるため、血糖値の上昇が比較的緩やかです(食後の血糖値の上昇スピードを示すGI値は高めですが、他の食品との組み合わせで調整可能です)。
さらに、お米のデンプン構造のおかげで腹持ちが良く、間食や次の食事での食べ過ぎを防ぐ効果が期待できます。ダイエット中こそ、適量のご飯で空腹を満たすことは大切です。
3. 日本型食生活の優秀な「軸」
農林水産省なども推奨する、昔ながらの「一汁三菜」を中心とした日本型食生活は、お米を軸にしています。
この食生活は、低脂質・高炭水化物(適度なタンパク質と食物繊維)のPFCバランスが取れており、世界でも健康的な食事スタイルとして評価されています。お米を減らすことで、代わりに脂質(肉や油物)の摂取が増えてしまい、かえって太るケースも多いのです。
【重要】太らない「ごはんの食べ方」3つの鉄則!
お米そのものは敵ではありませんが、「食べ方」を間違えると、もちろん太ります。賢くお米を食べて痩せるためのポイントはこちら!
1. ご飯の「量」とおかずの「質」を見直す
- 適量を守る: 自分の活動量に見合ったご飯の量を食べる(茶碗1杯分など)。おかわりは控える。
- 脂質の多いおかずを減らす: ご飯が進む、脂っこいおかず(揚げ物など)や濃い味付けの副菜を減らすことが、カロリーオーバーを防ぐ最大のカギです。
2. 玄米・雑穀米を積極的に取り入れる
白米はGI値が高めですが、玄米や雑穀米は食物繊維が豊富で、より**血糖値の上昇が緩やか(低GI)**です。これらを取り入れることで、太りにくい食べ方に近づきます。
3. 食事の「順番」と「時間」を意識する
- 野菜・汁物ファースト: まず野菜やきのこ、海藻など食物繊維が多いものから食べ始めると、血糖値の急上昇を防げます。
- 夜遅い時間は控える: 夜22時以降は、脂肪を溜め込みやすい体内時計の働きが活発になるため、夕食はできるだけ早く済ませましょう。
お米を我慢しなくて大丈夫!
「お米は太る」という説は、現代のダイエットブームの中で生まれた誤解に過ぎません。
お米は私たち日本人の体に必要なエネルギー源であり、脂質が少なく、調理法もシンプルな優秀な主食です!
食べるのを我慢するストレスよりも、**「適量を守り、バランスの良いおかずと組み合わせる」**という食べ方の工夫で、美味しく健康的に、ご飯と付き合っていきましょう!
皆さんの今日のご飯も、きっと美味しいはず。
江戸時代の人は1日に5合も食べていた
突然ですが、江戸時代の人たちって1日にどれくらいご飯を食べていたと思いますか?
現代の私たちが聞くと、びっくりするような量だったんですよ!
今日は、江戸っ子の豪快な食生活を覗いてみましょう!
衝撃!江戸時代の成人男性の米の消費量は?

結論から言ってしまうと、江戸時代の成人男性が1日に食べていたお米の量は、なんと平均で5合が目安だったと言われています!
- 1日あたり:5合
- (換算すると、約750g!)
資料によっては4合〜5合、力仕事をする人だと6合〜7合に達することもあった、という記述も見られますが、5合というのが一つの大きな目安として語られています。
現代の私たちと比べると…?
現代の日本人の平均的なお米の消費量は、1人あたり1日2合程度と言われています。
5合というと、現代の私たちが食べる量の2倍以上!毎食どんぶりに山盛りご飯、といったイメージでしょうか。
想像するだけでお腹がいっぱいになりそうです(笑)。
なぜ、江戸っ子はそんなに食べていたの?
これほど大量のご飯を食べていたのには、いくつかの理由があります。
1. 身体を動かすためのエネルギー源
江戸時代は、移動手段も仕事も人力が中心。町人や職人は朝から晩まで活発に動き回り、非常に多くのエネルギーを消費していました。
お米は、その重労働に耐えうる主要なエネルギー源だったんですね。これだけ食べないと、カロリーが足りなかったと考えられます。
2. 食事の主役は圧倒的に「米」だった
当時の庶民の食事は、基本的に一汁一菜(汁物と、主菜または副菜一品、そしてご飯)が基本です。
- 朝食:温かいご飯、味噌汁、漬物
- 昼食・夕食:冷や飯、味噌汁、少なめのおかず(煮物や焼き魚など)
肉食が一般的ではなく、魚も高級品だったため、おかずで栄養を補うというよりも、ご飯を大量に食べることで必要なカロリーを確保していたんです。ご飯こそが、文字通りの主食でした。
3. 江戸では白米が手に入りやすかった
地方の農村では麦飯や雑穀を混ぜたご飯が一般的だった時代も、大消費地である江戸には全国から大量の米が集まりました。
また、精米技術の向上により、庶民でも白米が日常的に食べられるようになったことも、ご飯の消費量を増やした一因と考えられています。
食べ過ぎの落とし穴:「江戸わずらい」
しかし、大量の白米に偏った食生活には大きな落とし穴もありました。
白米は精米の過程で、ビタミンB1がほとんど失われてしまいます。そのため、江戸っ子はビタミンB1欠乏症にかかる人が多く、これが「脚気(かっけ)」という病気を引き起こしました。
この脚気は、倦怠感や足のしびれ、ひどくなると心臓に影響を及ぼし、多くの人を苦しめました。原因不明の病として「江戸わずらい」と呼ばれたほど、江戸の町で蔓延していたんです。
江戸時代の成人男性が1日に食べていたお米の量は、なんと5合!
現代の私たちから見ると驚きの量ですが、それは当時の人々の重労働と、おかずが少ない食生活を支えるための、必要不可欠なエネルギーだったんですね。
現代の食生活は豊かになり、米の消費量は減りましたが、昔の人々の力強い食生活を知ると、日々の食事への感謝も深まりますね。
江戸時代の人が食べていたのは玄米?白米?
江戸っ子が1日に5合もご飯を食べていたという豪快な話を紹介しました。
「じゃあ、そのご飯って玄米?それとも白米?」と気になりますよね。
実は、江戸時代のご飯事情は、住んでいる場所によって大きく異なり、そしてある恐ろしい病の流行と深く関わっているんです。
場所によって「主食」が違った!
江戸時代のお米の事情をシンプルにまとめると、こうなります。
| 地域 | 主食としていたお米 | 特徴 |
|---|---|---|
| 江戸(都市部) | 白米(精米した米) | 富の象徴。「江戸患い」の原因に。 |
| 農村・地方 | 雑穀や麦を混ぜた「かて飯」 | 栄養バランスが良く、玄米に近い分付き米も主流。 |
1. 「江戸」は白米がステータスだった!
現代の私たちが当たり前に食べている白米は、もともと貴族など身分の高い人しか食べられない高級品でした。
しかし、江戸時代の中期(元禄の頃)になると、状況が変わります。
- 流通の発達: 全国から年貢米が江戸に集まり、精米技術(水車小屋など)も発達したことで、庶民でも白米が手に入りやすくなったのです。
- 「白米が食える!」: 地方から江戸に職を求めてやってくる人々にとって、白米を腹いっぱい食べられることは「江戸っ子」のステータスであり、大きな魅力でした。
こうして、特に江戸市中の人々は、こぞって白米を中心とした食生活を送るようになりました。
2. 農村や地方は「健康志向」だった!?
一方、江戸から離れた農村部では、必ずしも白米ばかりではありませんでした。
- 「かて飯(かてめし)」: 米に麦、粟(あわ)、稗(ひえ)などの雑穀を混ぜて炊いたご飯が主流でした。
- 分付き米: また、精米度の低い分付き米(玄米に近い米)も多く食べられていました。
これは、食料事情もありますが、結果的にビタミンや食物繊維が豊富な食事となっていました。
白米ブームがもたらした悲劇:「江戸患い」
白米食が普及した江戸の町で、やがて奇妙な病気が大流行しました。それが「脚気(かっけ)」です。
地方から江戸に来た武士や富裕層が、急に手足のしびれやむくみ、倦怠感を訴え、ひどい場合は命を落とすこともありました。
不思議なことに、その人が故郷(農村など)に帰ると症状が治まることが多かったため、この病気は**「江戸患い(わずらい)」**と呼ばれて恐れられました。
なぜ白米が原因だったのか?
脚気の原因は、後にビタミンB1の欠乏だと判明します。
- お米の胚芽(はいが)や米ぬかに豊富に含まれるビタミンB1は、精米して白米にする過程でほとんど取り除かれてしまいます。
- 江戸っ子は、一汁一菜というシンプルな食事で、大量の白米を食べていたため、ビタミンB1が極端に不足してしまったのです。
栄養豊富な雑穀や分付き米を食べていた農村の人々には、ほとんど見られない病気だったため、「江戸わずらい」は、白米食という食文化がもたらした悲劇だったと言えるでしょう。
江戸時代の「ご飯」は、住む場所と身分によって、白米と雑穀・玄米に分かれていました。
- 江戸で白米を食べることができたのは、平和と流通が発達した江戸時代の繁栄の証し。
- しかし、その裏側で、白米に偏りすぎた食生活が「江戸わずらい」という病気を引き起こしてしまいました。
**「栄養バランスが大切だよ!」**と、江戸時代の人々が身をもって教えてくれているようですね。現代の私たちも、玄米や雑穀の良さを見直し、バランスの取れた食事を心がけたいものですね。
江戸時代の肥満率は?
江戸時代の人が1日に5合ものご飯を食べていたという話をしましたよね?
「そんなに食べて太らないの?」という疑問、当然湧いてきますよね!
今日は、江戸時代の肥満率という、ちょっと興味深いテーマに迫ってみましょう!
結論:現代のような「肥満」は珍しかった!
現在の日本は、成人男性の約3割、女性の約2割が肥満とされています(これはこれで大きな問題ですが…)。
では、江戸時代はどうかというと、正確な「肥満率」を示す統計データはありませんが、当時の記録や文献、人々の体型から推測される結論は、
現代的な「肥満」の人は非常に少なかった
ということです。
現代の私たちが持つ「肥満」という概念(BMIに基づいた定義など)自体が、産業革命以降、食生活や労働環境が大きく変化した明治時代あたりから生まれたという指摘もあります。
なぜ太らなかったの? 3つの大きな理由!
あれだけ白米を食べていたのに、なぜ太る人が少なかったのでしょうか?それには、当時の生活スタイルと食生活に隠された秘密があります。
1. 圧倒的な運動量と消費カロリー
江戸時代の生活は、とにかく身体を動かすことが基本でした。
- 移動手段は徒歩: 現代のような車や電車はありません。町人も武士も、移動は基本的に自分の足。飛脚や駕籠かき(かごかき)といった職業の人たちは、今でいうウルトラマラソンランナーのようなものです。
- 肉体労働: 職人や農民は、朝から晩まで重い肉体労働に従事していました。
- 結論: 1日に5合ものご飯を食べていたのは、その膨大な活動量を維持するために、必要なエネルギーだったからです。摂取カロリーと消費カロリーのバランスが取れていたんですね。
2. 極端に低い「脂質」の摂取量
これが最も大きな理由かもしれません。江戸時代の食生活は、現代と比べて極端に脂質の摂取量が少なかったのです。
- 肉は高級品: 牛や豚などの四足動物の肉は、仏教の教えや流通の問題から日常的に食べられていませんでした(食べるとしても「薬喰い」)。卵も非常に高価でした。
- 調理法: 揚げ物や炒め物は少なく、調理の基本は煮る、焼く、蒸す。油の使用が限定的だったため、総エネルギー摂取量に占める脂質の割合は非常に低かったと考えられています。
- ご飯のメリット: お米は他の主食(パンなど)と違い、水だけで炊くため脂質を含みません。高カロリーの原因となる脂質の摂取が抑えられていたことが、太りにくさに直結しました。
3. 一汁一菜と「腹八分目」の教え
当時の庶民の食事は、ご飯と味噌汁と漬物を中心とした一汁一菜が基本でした。
また、江戸時代の養生訓(健康に関する書物)には、儒学者・医師である貝原益軒によって、現代にも通じる教えが記されています。
- 「腹八分目に」
- 「しつこくて脂っこいものをたくさん食べてはいけない」
質素でバランスの取れた和食を基本とし、過食を慎む精神が根付いていたことも、肥満を防ぐ要因となりました。
豪快な食生活の裏の「江戸わずらい」
ただし、健康に全く問題がなかったわけではありません。
大量の白米に偏り、副菜(おかず)が少なかったために、ビタミンB1が不足し、「脚気(かっけ)」という病気が大流行しました。
これは「江戸わずらい」と呼ばれ、特に白米をたっぷり食べられる裕福な武士や町人の間で深刻な問題となりました。太りすぎてはいなかったものの、栄養バランスの偏りという別の健康問題を抱えていたのです。
まとめ:江戸の知恵を現代に活かす!
江戸時代の人は、現代の私たちとは比べ物にならないほど身体を動かし、極めて低脂質の食生活を送っていました。
「ご飯(炭水化物)をしっかり摂りながら、徹底的に脂質を抑え、よく動く」
この江戸っ子の生活こそ、現代の私たちが学ぶべき健康的な体型を保つ秘訣なのかもしれませんね!
皆さんも、江戸の知恵を取り入れて、健康的な生活を送ってみませんか?

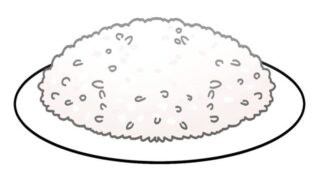


コメント