今、日本国内で拳銃を職務上使用できる職業は、法律で厳格に定められ主に以下の職業が拳銃を使用できます。
日本で拳銃が使える職業

- 警察官: 職務遂行上、必要と認められた場合に拳銃の使用が許可されています。
- 海上保安官: 海上における犯罪の取締りや、警備活動において拳銃の使用が認められています。
- 自衛官: 防衛任務や、治安維持活動において拳銃の使用が認められています。
- 刑務官: 刑務所内での警備や、受刑者の移送時などに拳銃の使用が認められています。
- 麻薬取締官: 麻薬犯罪の捜査や、取締りにおいて拳銃の使用が認められています。
- 入国警備官: 外国人の強制退去や、入国管理業務において拳銃の使用が認められています。
- 税関職員: 税関での取締業務において拳銃の使用が認められています。
これらの職業であっても、拳銃の使用は必要最小限に留められ、厳格な法的規制の下で行われます。
一般の人が護身用などの目的で拳銃を所持することは、日本では銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)により原則として禁止されています。
昔郵便局員も拳銃を使用できた

昔の日本では、郵便配達員が拳銃を所持することが許可されていた時代がありました。
背景:
- 明治時代の初期、郵便制度が始まった頃は、現金書留など貴重な郵便物を運ぶ郵便配達員が強盗に襲われる事件が多発しました。
- また、山間部などでは、熊などの野生動物による危険もありました。
経緯:
- 1873年(明治6年)に「短銃取扱規則」が制定され、郵便配達員に拳銃の所持が許可されました。
- その後、現金書留の取扱量が増加したため、1887年(明治20年)に「郵便物保護銃規則」が制定され、さらに厳格な規定の下で拳銃の所持が認められました。
- この事実は、警察官が拳銃を所持するよりも早い時期に、郵便配達員が武装していたことを示しています。
- この制度は、1949年(昭和24年)まで法律上は許可されていました。
補足:
- 東京都墨田区にある郵政博物館には、実際に郵便配達員に支給されていた拳銃が展示されています。
最後に
このように、昔の郵便配達は、現代では想像もつかないほど危険を伴う業務であったことがわかります。


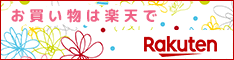


コメント