ども!今日は刑事ドラマなんかでよく聞くけど、意外と違いが分かりにくい
**「留置所(留置場)」
と
「拘置所」**について、詳しく解説していね!👮♂️🏛️
留置所と拘置所の大きな違い、それは「誰が管理しているか」と「いつ入るか」
留置所も拘置所も、罪を犯したとされる人(被疑者や被告人)の身柄を拘束する施設という点では共通しているんだけど、実は運営機関や収容のタイミングが大きく違うんだ。
| 施設名 | 運営機関 | 主な収容対象者 | 収容されるタイミング | 施設数(目安) |
|---|---|---|---|---|
| 留置所(留置場) | 警察(警察署内にある) | 逮捕・勾留された被疑者 | 逮捕直後から起訴されるまで(実務上) | 全国に約1,100~1,300か所 |
| 拘置所 | 法務省(矯正施設) | 勾留された被疑者・被告人、死刑囚など | 起訴後に留置所から移送されることが多い | 全国に本所8か所、支所100か所程度 |
1. 運営機関の違い
- 留置所は「警察」:警察署の中に設置されていて、警察官が管理しているよ。捜査活動の拠点に近い場所だね。
- 拘置所は「法務省」:法務省が管轄する**刑事施設(矯正施設)**の一つで、刑務所と同じ系統なんだ。警察とは独立した機関が管理しているから、取り調べなどの捜査活動からは距離が置かれているのが特徴。
2. 収容の対象とタイミングの違い
- 留置所:主に**逮捕・勾留された「被疑者」が入る場所。本来は逮捕から検察への送致までのごく短い期間(最大72時間)留め置くための施設なんだけど、拘置所が少ないから、実際には勾留が決定した後も、起訴されるまでの間、そのまま留置所に収容されるケースが多いんだ(これを「代用刑事施設」**というよ)。
- 拘置所:法律上は、刑が確定していない人(未決拘禁者)を収容するための施設。具体的には、勾留された**「被疑者」や、起訴されて裁判を待つ「被告人」、そして「死刑確定者」**などが収容されるよ。実務では、起訴された後に、留置所から拘置所に移送されることが一般的だよ。
施設での生活の違い(おまけ)
施設によって、生活の様子も少し変わってくるんだ。
- 食事🍚:
- 留置所:調理施設がないため、業者が作ったお弁当が支給されることが多いよ。
- 拘置所:受刑者が調理する一汁三菜の食事が提供されることが多く、留置所より充実しているという声もあるみたい。どちらも「自弁購入」(お菓子やカップ麺などを自費で購入)ができる場合があるよ。
- 面会👨👩👧:
- 留置所:一般の面会者(家族など)は、回数や時間に制限が厳しいことが多い。
- 拘置所:留置所よりは面会や差し入れの制限が緩やかになる傾向があるよ。ただし、どちらの施設も、弁護士との面会(接見)は比較的自由にできることになっているんだ。
留置所は**「警察の管理下で、主に捜査の初期段階に利用される施設」、拘置所は「法務省の管理下で、主に起訴後の裁判待ちの段階に利用される施設」**と覚えておくと分かりやすいね!
刑事施設での生活の様子について弁護士が解説している動画はこちらだよ: 留置場と拘置所の違い【弁護士が解説】
この動画は、留置所と拘置所の違いについて、法律的な観点から詳しく解説しているから関連性が高いよ。
続いては、ニュースで刑事事件の報道を見ると、「○○容疑者」という言葉をよく耳にしますよね。
でも、弁護士さんのコラムなどでは「○○被疑者」という言葉が出てくることがあります。
たった一文字違いですが、実はこの二つの言葉には、**「公的な立場の違い」**があるんです。
今日は、この「容疑者」と「被疑者」の違いについて、スッキリ整理してみませんか!
💡 ズバリ!「被疑者」が法律用語です
結論から言うと、この二つの言葉の指し示す意味はほぼ同じです。
どちらも「犯罪の嫌疑をかけられ、捜査の対象になっている人」を意味します。
しかし、その言葉が使われる場所が違います。
1.【被疑者(ひぎしゃ)】の正体 ⚖️
**「被疑者」**は、日本の法律(刑事訴訟法)で定められた正式な用語です。
- 誰が使う?: 警察官、検察官、裁判官、弁護士といった法律の専門家や捜査機関が、公的な文書や手続きの中で使います。
- いつ呼ばれる?: 犯罪の捜査が始まり、特定の人物に嫌疑がかかった段階から、検察官に「起訴」されるまでの期間、この呼び名が使われます。
- 意味: 彼は**「疑いをかけられている人」であり、裁判で有罪が確定するまでは、法的には「無罪の推定」**が働いています。
2.【容疑者(ようぎしゃ)】の正体 📺
**「容疑者」**は、法律用語ではありません。
- 誰が使う?: 主に新聞、テレビ、インターネットなどの**マスコミ(報道機関)が使っている報道用語(俗語)**です。
- なぜ使う?: 法律用語の「被疑者(ひぎしゃ)」が、発音のよく似た「被害者(ひがいしゃ)」と聞き間違えられやすいため、混乱を避ける目的でマスコミが独自に使い始めた、というのが一般的な説です。
- 意味: 法律上の「被疑者」とほぼ同じ人を指しますが、「容疑」という言葉から、より一般的な人にも疑いがかかっていることが分かりやすい、という側面もあります。
🔄 刑事事件での呼び名の変化
刑事事件の流れの中で、人の呼び名は以下のように変化していきます。
| 段階 | 呼び名 | 誰が使うか |
|---|---|---|
| 捜査対象の初期 | 被疑者(容疑者) | 法律家・捜査機関(報道) |
| \Downarrow 起訴(検察官が裁判にかけると決めること) | ||
| 裁判を受けている間 | 被告人 | 法律家・捜査機関・報道 |
| \Downarrow 有罪確定 | ||
| 刑務所にいる間 | 受刑者 | 法律家・刑務所など |
まとめ
日常生活でニュースを見るときは、「容疑者」=**「(法律上の)被疑者」**だと思っておけばOKです。
しかし、法律を扱う場面や、人権に関わる話をするときは、**「被疑者」**という正式な法律用語を使う方が、より正確でプロフェッショナルな表現になりますよ!
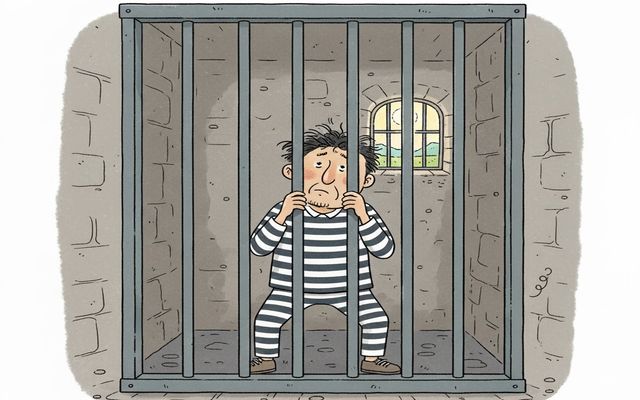



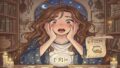
コメント