乳酸菌は、糖を分解して乳酸を作る細菌の総称です。
ヨーグルトやチーズなどの乳製品、漬物、味噌、醤油など、多くの発酵食品に含まれており、私たちの健康に様々な良い影響をもたらすと言われています。
死んでも活躍! 乳酸菌

乳酸菌の種類
乳酸菌は非常に多くの種類が存在し、その数は2000種類以上とも言われています。
代表的なものとしては、以下のようなものがあり、その中でも特に研究が進んでおり、健康効果が期待されている有名な乳酸菌をいくつかご紹介します。
代表的な乳酸菌
- ラクトバチルス・ブルガリクス (Lactobacillus bulgaricus): ヨーグルトの製造に欠かせない菌で、整腸作用などが知られています。
- ストレプトコッカス・サーモフィラス (Streptococcus thermophilus): こちらもヨーグルトの製造によく使われ、ブルガリクス菌と共存することでより良い発酵を促します。
- ラクトバチルス・アシドフィルス (Lactobacillus acidophilus): 腸内に常在する菌で、整腸作用や免疫力向上効果などが期待されています。
- ラクトバチルス・カゼイ (Lactobacillus casei): 乳酸菌飲料などに多く含まれ、免疫機能の調整や整腸作用などが報告されています。シロタ株(Lactobacillus casei Shirota)もこの一種です。
- ビフィドバクテリウム属 (Bifidobacterium): ビフィズス菌として広く知られ、乳酸だけでなく酢酸も生成し、整腸作用や免疫力向上に関わるとされています。ビフィドバクテリウム・ロンガム (Bifidobacterium longum) やビフィドバクテリウム・ブレーベ (Bifidobacterium breve) など、多くの種類があります。
- ラクトバチルス・ガセリ (Lactobacillus gasseri): 近年研究が進んでおり、内臓脂肪の低減や免疫機能への影響などが報告されています。
- ラクトバチルス・ラムノサス (Lactobacillus rhamnosus): アレルギー症状の緩和や免疫機能の調整に関与する可能性が示唆されています。GG株(Lactobacillus rhamnosus GG)が有名です。
- ラクトコッカス・ラクチス (Lactococcus lactis): チーズや乳製品の製造に古くから利用されており、近年では免疫機能への影響も研究されています。
- エンテロコッカス・フェカリス (Enterococcus faecalis): もともと人の腸内に存在する菌で、免疫活性化作用などが研究されています。EC-12株などが知られています。
- ロイコノストック・メセンテロイデス (Leuconostoc mesenteroides): 漬物などの発酵食品に含まれ、整腸作用や抗酸化作用などが期待されています。
特定の効果で知られる乳酸菌
- 1073R-1乳酸菌 (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus OLL1073R-1): 明治が発見したブルガリア菌の一種で、免疫力を高める効果が研究されています。
- L-92乳酸菌 (Lactobacillus acidophilus L-92株): カルピス社が研究した乳酸菌で、アレルギー症状の緩和や免疫機能の維持に役立つとされています。
- プラズマ乳酸菌 (Lactococcus lactis strain Plasma): キリンが研究した乳酸菌で、免疫細胞の司令塔であるpDC(プラズマサイトイド樹状細胞)を活性化する特徴があります。
乳酸菌の健康効果

乳酸菌は、主に以下のような健康効果が期待されています。
- 整腸作用: 腸内の善玉菌を増やし、悪玉菌の増殖を抑えることで、腸内環境を整えます。これにより、便秘や下痢の改善、消化吸収の促進などが期待できます。
- 免疫力向上: 腸は免疫細胞の多くが存在する場所であり、腸内環境を整えることは免疫機能の活性化につながります。風邪やインフルエンザなどの感染症予防や、アレルギー症状の緩和などが期待されています。
- 内臓脂肪の低減: 一部の乳酸菌には、内臓脂肪を減らす効果が示唆されています。
- 美肌効果: 腸内環境が改善されることで、肌荒れやニキビの予防、肌の水分量やバリア機能の改善などが期待できます。
- その他: コレステロール値の低下、高血圧のリスク低下、ピロリ菌の活動抑制など、様々な効果が研究されています。
乳酸菌を多く含む食品
- ヨーグルト
- チーズ
- 乳酸菌飲料
- 漬物(ぬか漬け、キムチなど)
- 味噌
- 醤油
- 納豆(発酵過程で乳酸菌が増えることがあります)
効果的な摂取方法
- 継続的に摂取する: 乳酸菌の効果を実感するためには、毎日 꾸준히 摂取することが大切です。
- 様々な種類の乳酸菌を摂る: 菌の種類によって効果が異なるため、色々な食品から多様な乳酸菌を摂取することが望ましいです。
- 生きたまま腸に届ける工夫: 生きた乳酸菌を摂取することが重要ですが、胃酸に弱いものもあるため、食後に摂取したり、カプセルなどで保護されたサプリメントを利用するのも有効です。
- プレバイオティクスと一緒に摂る: オリゴ糖や食物繊維など、善玉菌のエサとなるプレバイオティクスを一緒に摂取することで、乳酸菌の増殖を助け、より効果を高めることができます。
乳酸菌は私たちの健康維持に役立つ可能性を秘めた微生物です。日々の食生活に意識して取り入れて、健やかな毎日を送りましょう。
また乳酸菌は、様々な食品やサプリメントに含まれており、私たちの健康維持に役立つ可能性があります。
ただし、効果には個人差があり、菌の種類によって期待できる効果も異なるため、ご自身の目的に合わせて選ぶことが大切です。
死んでも活躍する乳酸菌
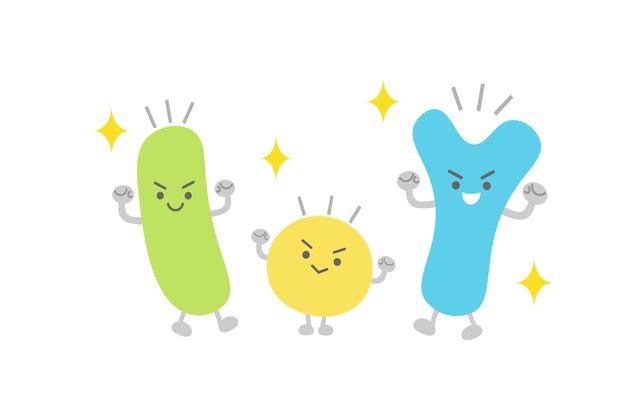
乳酸菌は、摂取した全てが生きて腸に届くわけではありません。
胃酸は非常に強い酸性であり、多くの乳酸菌は胃を通過する際に死滅してしまいます。
しかし、「乳酸菌は胃液で死んでしまうから効果がない」というのは間違いです。
死んだ乳酸菌にも以下のような効果が期待されています。
- 腸内細菌叢の改善: 死菌となった乳酸菌は、腸内の善玉菌のエサとなり、善玉菌の増殖を助けることがあります。
- 免疫刺激: 死菌が腸の免疫細胞を刺激し、免疫力を高める効果が報告されています。
生きたまま腸に届けるための工夫もされています。
- 食後に摂取する: 空腹時は胃酸の濃度が高いため、食後に摂取することで胃酸の影響を和らげることができます。
- 胃酸に強い菌を選ぶ: ラクトバチルス・アシドフィルスやビフィズス菌の中には、比較的胃酸に強い菌株も存在します。
- カプセルやコーティング: 胃酸で溶けにくい特殊なカプセルやコーティングで乳酸菌を保護し、腸まで届きやすくする製品もあります。
- 植物性乳酸菌: 一般的に、動物性乳酸菌よりも植物性乳酸菌の方が酸に強い傾向があると言われています。
生きた乳酸菌と死んだ乳酸菌の働きの違い
腸まで生きて届く乳酸菌と、胃酸などで死んでしまう乳酸菌では、働き方に違いがあります。
それぞれの特徴を理解することで、より効果的な乳酸菌の摂取に繋がります。
腸まで生きて届く乳酸菌の働き
- 定着と増殖: 生きたまま腸に到達した乳酸菌は、腸内環境が適していれば腸壁に定着し、増殖することができます。これにより、善玉菌の割合を直接的に増やし、悪玉菌の増殖を抑制する効果が期待できます。
- 乳酸やその他の有用物質の産生: 生きた乳酸菌は、糖を分解して乳酸を作り出します。乳酸は腸内を酸性に保ち、悪玉菌の増殖を抑えるとともに、腸の蠕動運動を促進する働きがあります。また、菌の種類によっては、ビタミン類や短鎖脂肪酸などの有用な物質を産生することもあります。
- 免疫細胞の活性化: 生きた乳酸菌は、腸管免疫系の細胞に直接働きかけ、免疫機能を活性化させることが知られています。これにより、感染症予防やアレルギー症状の緩和などが期待されます。
- 腸内フローラの多様性維持: 様々な種類の生きた乳酸菌を摂取することで、腸内フローラのバランスを整え、多様性を維持するのに役立ちます。
死んでしまう乳酸菌の働き
- 善玉菌のエサとなる(バイオジェニックス): 死菌となった乳酸菌は、腸内細菌の栄養源となり、特にビフィズス菌などの善玉菌の増殖を間接的に助けることがあります。これは「バイオジェニックス」と呼ばれる考え方です。
- 免疫刺激作用(免疫賦活): 死菌の菌体成分(細胞壁など)が、腸管免疫系の細胞を刺激し、免疫機能を活性化することが報告されています。生菌に比べて定着や増殖の機能はありませんが、免疫系への刺激という点で一定の効果が期待できます。
- 腸管のバリア機能の改善: 一部の研究では、死菌が腸管のバリア機能を高める可能性が示唆されています。
- 整腸作用: 死菌が腸内の水分バランスを調整したり、便通を改善したりする効果が報告されています。これは、菌体成分が物理的に腸を刺激するためと考えられています。
さいごに
生きた乳酸菌と死んだ乳酸菌のどちらが良いかは一概には言えません。
それぞれの菌株や摂取する目的によって、適したものが異なります。
- 生きた乳酸菌: より直接的な整腸作用や免疫活性化、腸内フローラの改善を期待する場合に適しています。
- 死んだ乳酸菌: 生菌が胃酸に弱い場合や、免疫刺激作用を主な目的とする場合に有効です。また、保存性や安定性に優れているというメリットもあります。
最近では、生菌と死菌の両方を配合した製品も多く見られます。
これは、それぞれの利点を活かすためと考えられます。
重要なのは、継続的に摂取すること、そしてご自身の体調や目的に合わせて適切な種類の乳酸菌を選ぶことです。
製品に表示されている菌の種類や数を参考に、色々な情報を集めて試してみる事がおススメです。



コメント