日本の株価が過去最高益を記録する一方で、多くの国民の生活が豊かになったと実感できない理由には、いくつかの複雑な要因が絡み合っています。
日本の株価が最高益を出しても生活が豊かにならない理由
1. 企業収益と賃金の乖離
株価は主に企業の収益性や将来性への期待を反映します。
近年、日本の上場企業は円安やコスト削減、グローバルな需要増などを背景に過去最高益を更新しています。
しかし、この増益分が必ずしも従業員の賃金上昇に直結しているわけではありません。
企業は、将来の不確実性に備えて内部留保を厚くしたり、株主還元を優先したりする傾向があります。
このため、企業がどれだけ儲けても、それが働く人々の給料に反映されず、実質的な購買力が向上しないという状況が起きています。
2. 物価上昇による実質賃金の低下
近年の物価上昇は、多くの人々の家計を圧迫しています。
名目賃金(額面上の給料)がわずかに上昇したとしても、物価の上昇率がそれを上回る場合、実質賃金はマイナスになります。
つまり、給料が増えても、以前と同じものを買うのにより多くのお金が必要になり、結果的に生活が苦しくなるという事態が生じているのです。
3. 株高の恩恵を受ける層の偏り
日本の株式を保有しているのは、主に富裕層や高齢者、機関投資家、そして外国人投資家です。
特に、個人の株式保有率は米国などに比べて低く、株式投資に積極的な層は限られています。
そのため、株価が上昇しても、その「資産効果」(株価上昇による消費意欲の向上)は一部の層に限定され、国民全体に広く行き渡るには至りません。
4. 経済格差の拡大
非正規雇用の増加や産業構造の変化、デジタル化の進展などにより、所得格差が拡大していることも、生活実感の低下につながっています。
賃金の低い非正規雇用者が増えたことで、全体の平均賃金が伸び悩んでいる側面があります。
また、同じ正規雇用者であっても、ITなどの専門性の高い分野とそうでない分野とで、賃金に大きな開きが生じ、格差が広がっているという指摘もあります。
5. 労働生産性の伸び悩み
日本の労働生産性は、欧米の先進国に比べて低い水準にとどまっています。
企業の収益性は改善されても、従業員一人ひとりが生み出す付加価値が大きく伸びていないため、構造的に賃金を大幅に引き上げることが難しい状況にあります。
以上の要因が複合的に作用し、日本の株価が最高益を記録していても、それが多くの国民の生活の豊かさに直結しないという現状を生み出しています。
生活を豊かにするためには、企業が利益を適切に賃金に還元すること、物価上昇を上回る賃上げが実現すること、そして経済格差を是正するような政策や取り組みが不可欠であると考えられます。
バブル時代との違いは何

バブル時代と現在の株価上昇は、その背景と経済への影響が大きく異なります。
1. 株価上昇の要因
- バブル時代: 多くの企業が本業の利益だけでなく、株や不動産といった資産の投機的な売買で利益を増やしました。当時の金融緩和政策により、企業や個人が低金利で多額の資金を借り入れ、それがさらなる資産購入を加速させるという、実体経済からかけ離れた株高・地価高騰が起きていました。
- 現在: 円安による輸出企業の業績向上や、コスト削減による企業収益の改善が主な要因です。また、海外投資家からの資金流入や、新NISAなどによる国内の投資家層の拡大も株価を押し上げています。バブル期のような投機的な要素だけでなく、企業の収益力向上が株価の裏付けとなっている点が大きな違いです。
2. 経済全体への波及
- バブル時代: 株高・地価高騰による資産効果で、多くの個人が富を実感し、消費が活発になりました。企業も利益を賃金や設備投資に回す余裕があり、社会全体が好景気に沸いていました。
- 現在: 株価が上昇しても、その恩恵は一部の富裕層や投資家、大企業に偏っています。多くの労働者の賃金は物価上昇に追いついておらず、実質賃金は低下傾向にあります。これにより、消費意欲が伸び悩み、株価上昇が国民の生活の豊かさに直結しているとは感じにくい状況です。
3. 株価のPER(株価収益率)
- バブル時代: 株価が企業の利益水準から見て異常に高い水準にあり、PERは平均で60~70倍に達することもありました。これは、将来の利益を過度に楽観的に見込んでいたためです。
- 現在: 現在の日経平均のPERはバブル期に比べて大幅に低く、企業の収益力を反映した健全な水準にあるとされています。株価は企業が実際に稼ぐ力に基づいて上昇している、と見なすことができます。
株価上昇で投資家たちだけでな、く普通に仕事している人たちにも恩恵がでる社会になって欲しいですね。
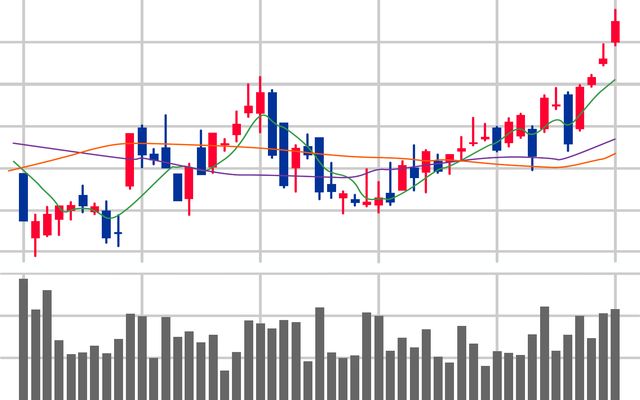


コメント