日本の消消費税はある国々と比べると安いと言う意見もありますが、税金に税金を課すなんておかしなことを平然としている国なので一概に数値だけで比べられないのは事実でです。
そんな中、特に酒税は世界で一番高いと言われています。
これって本当?
ただ日本の酒税が世界一高いというのは、一概には言えません。
しかし、特定のお酒の種類、特にビールにおいては、日本の酒税は国際的に見ても非常に高い水準にあります。
日本の酒税が世界一高い

以下にいくつかのポイントをまとめました。
- ビールの酒税が高い: 日本のビールにかかる酒税は、他の先進国と比較して非常に高いです。例えば、350ml缶ビールにかかる酒税は、ドイツの約20倍、アメリカの約12倍とも言われています(過去のデータに基づく比較であり、変動する可能性があります)。
- 酒税体系の複雑さ: 日本の酒税は、お酒の種類やアルコール度数などによって細かく税率が分かれており、複雑な体系となっています。
- 過去の経緯: ビールはかつて日本で高級品であったため、高い税率が設定されたという歴史的背景があります。
- 税制改正の動き: 近年、酒税の見直しが行われており、ビールや日本酒の税率が引き下げられる一方、発泡酒や第三のビール、チューハイなどの税率が引き上げられる傾向にあります。これは、類似する酒類間の税負担の公平性を図る目的があります。
- 他の酒類との比較: ビールが高い一方で、他の酒類、例えばワインなどは、輸入関税の撤廃などにより価格が下がる傾向もあります。
結論として、日本のお酒に対する税金全体が世界一高いとは言えませんが、ビールに関しては世界的に見ても高水準であると言えます。
日本のビールに対する税金が特に高い
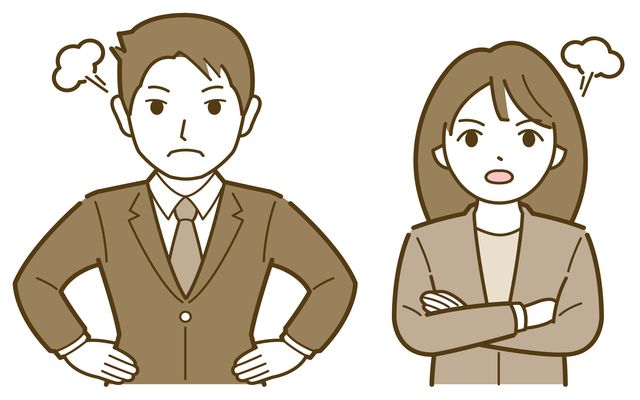
日本のビールに対する税金が特に高いのには、主に以下の歴史的な背景と税制上の理由があります。
1. 明治時代の高級品としての位置づけ:
- 日本でビールが初めて課税されたのは明治時代(1901年)のことです。当時、ビールは西洋から入ってきたばかりの高級品であり、一般庶民には手の届かない存在でした。
- このため、政府はビールを高所得者層が嗜むものと捉え、高い税率を設定しました。この時の税制の名残が、現代にも引き継がれていると考えられています。
2. 税収確保の手段:
- 明治時代以降、酒税は政府の重要な財源の一つでした。特に、ビールは他の酒類に比べて生産量が多く、安定した税収が見込めたため、高い税率が維持されてきました。
- 戦争などの際には、軍事費調達のために酒税が引き上げられることもありました。
3. 複雑な酒税体系:
- 日本の酒税は、お酒の種類やアルコール度数、原料などによって細かく税率が分かれています。この複雑な体系の中で、ビールは比較的高い税率が設定されたまま推移してきました。
- かつては、ビールの原料である麦芽の使用比率によって税率が異なり、発泡酒や第三のビールといった、より安価な代替品が登場する要因の一つとなりました。
4. 税制改正の動きと今後の見通し:
- 近年、類似する酒類間の税負担の公平性を図るため、酒税の見直しが進められています。
- 2020年10月にはビールの酒税が引き下げられ、発泡酒や第三のビールの税率が引き上げられました。
- 今後も段階的に税率が見直され、2026年10月にはビール、発泡酒、第三のビールの税率が一本化される予定です。これにより、ビールにかかる税負担は相対的に軽減される見込みです。
このように、日本のビール税が高い背景には、歴史的な経緯と、税収確保、そして複雑な税制体系が複合的に影響していました。
しかし、近年では税制改正により、その状況は変化しつつあります。
今後も酒税制度は改正される可能性があるため、是正されることを切望します。
なぜ酒税法が出来たのか?
酒税法ができた主な理由は、以下の通りです。
1. 財源の確保:
- 初期の目的: 明治時代に近代的な税制が整備される中で、酒税は政府の重要な財源の一つとされました。特に、日清戦争や日露戦争といった戦費調達の必要性から、酒税は増税の対象となり、安定した税収を確保する手段として重視されました。
- 税収の高さ: かつては、酒税収入は国税収入の中でも大きな割合を占めていました。
2. 酒造業の管理・監督:
- 免許制度: 酒税法は、酒類の製造や販売を行う業者に対して免許制度を設けることで、業界を管理・監督する役割を果たしています。これにより、粗悪な酒の製造や不正な販売を防ぐとともに、税の徴収を確実に行うことを目指しています。
- 品質管理: 間接的な効果として、免許制度は酒類の品質維持にもつながると考えられます。
3. 消費の調整:
- 奢侈品としての課税: かつてビールなどの酒類は高級品とみなされ、高い税率が課せられていました。これは、奢侈品の消費を抑制し、税負担を求めるという考え方に基づいています。
- 税率の調整: 近年では、酒類間の税負担の公平性を図るため、税率の見直しが行われています。これは、消費者の選択や市場の動向に税制が与える影響を考慮したものです。
歴史的な背景:
- 日本における酒への課税は古く、室町時代には酒麹の販売業者への課税が見られます。
- 江戸時代には、酒造業者に対して営業税のようなものが課されていました。
- 明治時代になり、近代的な税制が整備される中で、酒税は重要な財源としての地位を確立しました。
現在の酒税法は、昭和28年(1953年)に制定されたものが基本となっていますが、社会経済状況の変化や消費者の嗜好の変化に合わせて、何度か改正が行われています。
酒税に消費税が上乗せ?

酒税と消費税は、課税の目的と性質が異なるため、両方とも課税される仕組みになっています。
1. 酒税の目的と性質:
- 特定の物品への課税(個別消費税): 酒税は、特定のお酒類に対して課される税金です。これは、たばこ税やガソリン税などと同様に、特定の消費に対して課税される「個別消費税」という性質を持ちます。
- 財源の確保: 酒税は、国の重要な財源の一部となっています。
- 消費の調整: 歴史的には、奢侈品とみなされたお酒への課税を通じて、消費を抑制する目的もありました。
- 酒造業の管理・監督: 酒税法は、酒類の製造・販売業者を管理し、品質の維持や不正な取引を防ぐ役割も担っています。
- 間接税: 酒税は、製造者や輸入業者が納税義務者ですが、最終的には販売価格に上乗せされる形で消費者が負担する「間接税」です。
2. 消費税の目的と性質:
- 一般的な消費への課税(一般消費税): 消費税は、ほとんど全ての商品やサービスの消費に対して広く公平に課される税金です。「一般消費税」という性質を持ちます。
- 社会保障財源など: 消費税は、国の社会保障制度を支えるための重要な財源となっています。
- 間接税: 消費税も、事業者が納税義務者ですが、最終的には商品やサービスの価格に上乗せされる形で消費者が負担する「間接税」です。
なぜ両方課税されるのか:
- 課税対象の違い: 酒税は「お酒類」という特定の物品に課税されるのに対し、消費税は「ほとんど全ての商品やサービス」というより広い範囲に課税されます。
- 税の目的の違い: 酒税には、特定の産業の管理や歴史的な背景に基づく消費調整といった目的がある一方、消費税はより広く公平な財源確保を主な目的としています。
- 二重課税の議論: お酒の販売価格には既に酒税が含まれているため、その価格に対してさらに消費税が課されることは、「二重課税」であるという議論もあります。しかし、国は、酒税はあくまで個別消費税としてお酒の製造・販売という行為に課税されるものであり、消費税は最終的な消費という行為に課税されるもので、課税の段階と対象が異なると説明しています。
さいごに
このように、酒税と消費税は、それぞれの異なる目的と性質に基づいて課税されているため、お酒の購入時には両方の税金が合算された価格を支払う必要があるのです。
なんか納得出来ないですね。

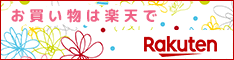


コメント