参議院の常任委員長について、簡単に解説します。
参議院の常任委員長ってなに?
1. 常任委員長とは
常任委員長とは、国会(衆議院・参議院)に常設されている「常任委員会」のトップのことです。
- 常任委員会:国会には、特定の分野(例えば、内閣、外交、財政など)ごとに設置されている委員会があります。これを常任委員会と呼び、参議院には現在17の委員会があります。
- 委員長:その常任委員会の運営を司るのが常任委員長です。公正な立場で委員会の議事を整理し、秩序を保持する役割を担います。
2. 常任委員長の役割
常任委員長の主な役割は以下の通りです。
- 委員会の議事進行:委員会での質疑、討論、採決などを仕切り、円滑に議論が進むようにします。
- 秩序の保持:委員会がスムーズに運営されるよう、委員会の秩序を保ちます。
- 委員会を代表する:委員会を代表して、本会議に委員会の審査結果を報告することもあります。
委員会は、国会に提出された法律案などを本会議にかける前に、専門的かつ詳細に審査する非常に重要な機関です。
そのため、その運営を担う常任委員長の役割は、国会の審議全体に大きな影響力を持っています。
3. 常任委員長の選出
参議院の常任委員長は、本会議で選挙によって選出されます。
慣例として、各会派(政党や政治団体)の所属議員数に応じて、常任委員長のポストが割り当てられます。
議席数の多い会派ほど、多くの委員長ポストを獲得する傾向にあります。
4. 参議院の常任委員会の例
参議院には以下の17の常任委員会があります。
- 内閣委員会
- 総務委員会
- 法務委員会
- 外交防衛委員会
- 財政金融委員会
- 文教科学委員会
- 厚生労働委員会
- 農林水産委員会
- 経済産業委員会
- 国土交通委員会
- 環境委員会
- 国家基本政策委員会
- 予算委員会
- 決算委員会
- 行政監視委員会
- 議院運営委員会
- 懲罰委員会
これらの委員会が、それぞれ所管する分野の議案や国政に関する事項について調査・審査を行います。
そして、その委員会のトップとして、各常任委員長が国会の重要な議論を動かしているのです。
参議院の17の常任委員会の内容
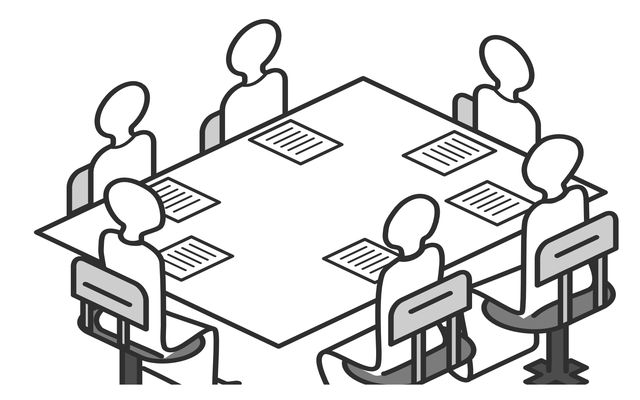
参議院の17の常任委員会は、それぞれ特定の分野の国政について、法律案の審査や調査を行います。
以下に、各委員会の主な内容をまとめました。
行政・国家運営に関する委員会
- 内閣委員会:内閣、内閣府、人事院、宮内庁、国家公安委員会など、国の行政全般に関わる事項を所管します。
- 国家基本政策委員会:国の基本的な政策、すなわち外交、防衛、財政、経済、社会保障など、国政の根幹に関わる事項について調査・議論します。
- 予算委員会:国会の最も重要な役割の一つである予算について審査します。各省庁の予算配分や使い道について詳細な質疑を行います。
- 決算委員会:国の予算が適切に使われたかどうか、決算を審査します。会計検査院の検査結果も踏まえて、無駄な支出がないかなどを厳しくチェックします。
- 行政監視委員会:行政の効率性や透明性などを監視し、国民からの行政に対する苦情処理も行います。
- 議院運営委員会:国会の運営全般を所管します。本会議の日程調整や、国会法などの法規に関する事項を扱います。
各省庁の所管事項に関する委員会
- 総務委員会:総務省の所管事項、具体的には地方自治、行政管理、情報通信、選挙制度などについて扱います。
- 法務委員会:法務省の所管事項、裁判所の司法行政に関する事項を扱います。
- 外交防衛委員会:外務省と防衛省、国家安全保障会議の所管事項を扱い、外交政策や防衛問題について審査・調査します。
- 財政金融委員会:財務省と金融庁の所管事項を扱い、国の財政や金融政策について議論します。
- 文教科学委員会:文部科学省の所管事項、教育、文化、学術、スポーツ、科学技術などについて扱います。
- 厚生労働委員会:厚生労働省の所管事項、医療、年金、福祉、雇用、労働問題など国民生活に直結する分野を扱います。
- 農林水産委員会:農林水産省の所管事項、農業、林業、水産業、食料自給率などについて扱います。
- 経済産業委員会:経済産業省、公正取引委員会の所管事項、経済政策、産業振興、貿易、エネルギーなどについて扱います。
- 国土交通委員会:国土交通省の所管事項、道路、鉄道、航空、港湾などのインフラ整備、観光、気象庁などについて扱います。
- 環境委員会:環境省、公害等調整委員会の所管事項、環境問題、公害対策、地球温暖化対策などについて扱います。
その他の委員会
- 懲罰委員会:議員が国会の秩序を乱すなどの行為を行った場合に、懲罰を科すかどうかの審査を行います。
これらの委員会は、それぞれ専門的な視点から、国政の多岐にわたる課題を深く掘り下げて議論し、国会における審議の基盤を形成しています。
参議院の任委員会と衆議院の常任委員会の違い
衆議院の常任委員会と参議院の常任委員会は、その役割や機能において大きな違いはありません。
どちらの議院でも、常任委員会は国の重要な法律案や予算案などを専門的かつ実質的に審議する場として機能します。
しかし、両院の委員会にはいくつかの細かな違いがあります。
主な違い
委員会の数と名称:
- 衆議院には17の常任委員会があります。
- 参議院には17の常任委員会があります。
- 委員会の名称はほぼ同じですが、一部、両院で異なる名称や所管事項を持つものもあります。
委員の数:
- 各委員会の委員の数は、衆議院と参議院で異なります。例えば、政治倫理審査会では、衆議院は25人、参議院は15人と規定されています。
参議院独自の委員会:
- 参議院には、常任委員会や特別委員会の他に、国政の基本的事項を長期的・総合的に調査する「調査会」という独自の機関があります。調査会は法律案の審査は行いませんが、調査の成果として法律案を提案することができます。
共通点
- 役割: 法律案や予算案などの議案を専門的に審査し、本会議に提出する。
- 委員長の選出: 委員長は本会議で選挙によって選出される。
- 委員の選任: 委員は、各会派の所属議員数の比率に応じて割り当てられ、議長の指名によって選任される。
これらの違いは、両議院の役割分担や運営方法の違いに起因するものです。
衆議院は「解散」があり、任期が4年であるのに対し、参議院は「解散」がなく、任期が6年で3年ごとに半数が改選されるという違いが、それぞれの議院の委員会運営にも影響を与えています。
![]()



コメント