子供の頃、友達と相撲をとるときに「ハッキョイ、のこった」という掛け声を合図にはじめていました。
また、「ハッキョイ、のこった」の掛け声をもとに始める光景を何回も見てきました。
しかし、これ間違いだそうです。
相撲の立ち合いの合図は「ハッキョイ、のこった」でない

相撲の立ち合いの合図は「ハッキョイ、のこった」ではありません。
「ハッキョイ」や「のこった」は、行司が力士を励ましたり、勝負の状態を伝えたりする際に発する言葉です。
立ち合いは、力士同士が呼吸を合わせ、両手を土俵についてから同時に立ち上がることで成立します。
行司が開始の合図を出すわけではありません。
ただし、行司は立ち合いが成立した直後や、取組中に力士の動きが止まった際に「はっきよい」(「はっけよい」とも言われます)と声をかけ、勝負を促します。これは「発気揚々(はっきようよう)」という言葉から来ており、「力を込めて精一杯戦え」という意味合いがあります。
また、力士が土俵際で粘っている際など、勝負がまだ決まっていない状況では、行司は「のこった」と声をかけます。
これは「まだ土俵に残っているぞ」「勝負はこれからだ」という意味です。
このように、「ハッキョイ」や「のこった」は立ち合いの合図ではなく、取組中に行司が発する掛け声なのです。
相撲は何故とると言うの?
「相撲を取る」という言い方の由来には、いくつかの説があり、有力な説の一つは、相撲の起源にあると考えられています。
相撲は、神話の時代から日本に存在するとされ、『古事記』や『日本書紀』には、神々が力比べをしたという記述があります。
この力比べの際、手を取り合って勝負を始めたことが、「相撲を取る」という言葉のルーツになったと言われています。
また、相撲の古い呼び方である「角力(すまい)」が、「争う」「競う」という意味を持つ「争(すまう)」という動詞から来ているという説もあります。
この「すまう」に、動作を表す接尾語の「う」がついたものが「すもう」となり、それがさらに「相撲を取る」という表現につながったと考えられます。
このように、「相撲を取る」という言い方には、神話の時代の力比べで手を取り合ったという起源や、「争う」という意味を持つ古い言葉が関係していると言われています。
相撲の番付
相撲の番付(ばんづけ)は、大相撲における力士の格付けを示すものです。
これは、力士の地位や実力を示すだけでなく、給与や待遇にも大きく影響する、非常に重要なものです。
番付の基本構造
番付は、大きく分けて以下の6つの階級に分かれています。
- 幕内(まくうち): 大相撲の最上位の階級。原則として定員は42名です。
- 十両(じゅうりょう): 幕内に次ぐ階級。定員は28名です。この階級以上の力士は「関取(せきとり)」と呼ばれ、月給が支給されるなど待遇が大きく向上します。
- 幕下(まくした): 十両の下の階級。定員は120名です。
- 三段目(さんだんめ): 幕下の下の階級。定員は約180名です。
- 序二段(じょにだん): 三段目の下の階級。定員はありません。
- 序ノ口(じょのくち): 最下位の階級。定員はありません。
幕内の格付け
幕内力士の中には、さらに細かな格付けが存在します。
- 横綱(よこづな): 番付の最高位。実力、品格ともに優れていると認められた力士が就任します。人数は固定されていません。
- 大関(おおぜき): 横綱に次ぐ地位。横綱不在の場合は、番付の筆頭となります。
- 関脇(せきわけ): 大関の下の地位。三役(さんやく)と呼ばれる上位陣の一角です。
- 小結(こむすび): 関脇の下の地位。こちらも三役の一員です。
- 前頭(まえがしら): 三役以下の幕内力士。さらに1枚目、2枚目…と順位付けされます。役が付かないため「平幕(ひらまく)」とも呼ばれます。
番付の決定方法
番付は、年6回開催される本場所の成績に基づいて編成されます。
- 勝ち越し: 15日間の本場所で勝ち星が負け星を上回ると、原則として番付が上がります。勝ち越しの数が多いほど、上がり幅も大きくなる傾向があります。
- 負け越し: 負け星が勝ち星を上回ると、原則として番付が下がります。負け越しの数が多いほど、下がり幅も大きくなる傾向があります。
- 新入幕・新十両: 幕下や三段目の力士が好成績を挙げると、十両や幕内に昇進することがあります。
- 陥落: 十両や幕内の力士が大きく負け越すと、下の階級に降格することがあります。
- 東西: 番付表は東方と西方に分かれており、原則として東の方が上位とされます。同じ成績の力士がいた場合、東方の力士が上位に残ることがあります。
番付表の見方
番付表は、各本場所前に日本相撲協会から発表されます。
- 最上段: 横綱、大関が中央に大きく書かれています。
- 2段目以下: 東方と西方に分かれ、右から左へ、上位から下位へと順に力士の名前が記載されています。
- 文字の大きさ: 横綱が最も大きく、以下、地位が下がるにつれて文字が小さくなります。
- 四股名: 力士の名前(しこ名)が書かれています。
- 成績: 前の場所の成績などが小さく記載されている場合があります。
番付は、力士にとって自身の努力の証であり、目標となるものです。
観戦する側にとっても、力士の地位や実力を把握する上で欠かせない情報源となっています。
相撲の歴史
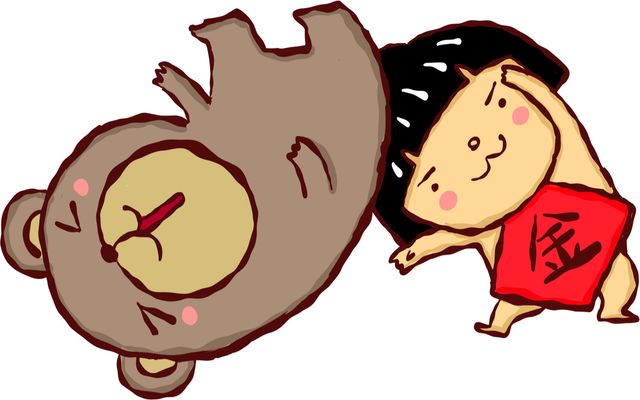
相撲の歴史は非常に古く、神話の時代にまで遡ると言われています。
力比べや農耕儀礼と深く結びつきながら、長い年月をかけて現在の形へと発展してきました。
起源と神話の時代
- 『古事記』や『日本書紀』には、国譲りの際に建御雷神(たけみかづちのかみ)と建御名方神(たけみなかたのかみ)が力比べをしたという記述があり、これが相撲の起源の一つと考えられています。
- 第11代垂仁天皇の時代には、野見宿禰(のみのすくね)と当麻蹶速(たいまのけはや)が天皇の前で天覧相撲を行ったという伝説があり、これが日本最古の相撲とされています。野見宿禰は相撲の神様としても祀られています。
- 古墳時代には、力士を模した埴輪が出土しており、この頃には既に力比べとしての相撲が行われていたと考えられています。
奈良・平安時代:宮廷行事としての相撲
- 奈良時代には、**相撲節会(すまいのせちえ)**と呼ばれる宮廷行事が行われるようになりました。これは、七夕の節会などの際に行われた余興の一つで、 страны各地から力士が集められ、天皇の前で相撲が披露されました。
- 平安時代にも相撲節会は引き続き行われ、宮廷の重要な儀式の一つとして定着しました。この頃の相撲は、単なる力比べだけでなく、豊作を祈願する神事としての意味合いも持っていました。
鎌倉・室町・戦国時代:武士の鍛錬としての相撲
- 鎌倉時代以降、武士の台頭とともに、相撲は武術の鍛錬としても重視されるようになりました。
- 戦国時代には、織田信長が相撲を好み、安土城で大規模な上覧相撲を開催したことが知られています。信長は、相撲で優秀な成績を収めた者を家臣として取り立てることもありました。
江戸時代:大衆文化としての発展
- 江戸時代に入ると、相撲は武士だけでなく、庶民の娯楽としても広く親しまれるようになりました。
- 各地で勧進相撲が行われるようになり、経済的な基盤を持つ職業としての力士が登場しました。
- 谷風梶之助、小野川喜三郎、雷電爲右エ門などの力士が現れ、相撲の人気は頂点に達しました。
- 現在の相撲の基礎となる土俵の形式などがこの時代に確立されました。
明治時代以降:国技としての確立と近代化
- 明治時代になると、相撲は日本の国技と位置づけられるようになります。
- 1909年には、両国に初の 施設である国技館が建設されました。
- 大日本相撲協会が設立されました。
- 近年では、海外出身の力士も活躍するなど、国際化も進んでいます。
このように、相撲は 古来より宮廷の儀式、武士の鍛錬、庶民の娯楽へと変化しながら、日本の文化と深く結びついて発展してきたのです。
さいごに
相撲は、ひと頃より人気に陰りがありますが歴史や仕組みなど少し知るだけでも面白さが増すと思います。



コメント