唐揚げと竜田揚げはどちらも人気の揚げ物ですが、明確な違いはあいまいになっています。
しかし、一般的には以下の違いがあります。
唐揚げと竜田揚げの違いは何?
唐揚げ
- 衣: 小麦粉を使うことが多いですが、片栗粉や両方を混ぜて使うこともあります。
- 下味: 本来は下味をつけないものとされていましたが、現在では醤油や生姜などで下味をつけるのが一般的です。
- 特徴: 幅広い食材(鶏肉、魚、野菜など)に使われる揚げ物の総称として使われることもあります。
竜田揚げ
- 衣: 片栗粉を使うのが一般的です。
- 下味: 醤油とみりんをベースにした下味をしっかりとつけるのが特徴です。そのため、揚げ上がりの色が唐揚げよりも濃く(赤褐色に)なる傾向があります。
- 名前の由来: 奈良県の紅葉の名所である竜田川の紅葉に、揚げ上がりの色を見立てて名付けられたという説が有名です。
まとめると…
| 項目 | 唐揚げ | 竜田揚げ |
|---|---|---|
| 衣 | 小麦粉が一般的(片栗粉や混合もあり) | 片栗粉が一般的 |
| 下味 | 本来はつけないが、現在はつけることが多い | 醤油とみりんベースの下味をしっかりつける |
| 色 | 比較的薄い色 | 赤褐色が特徴的 |
| 由来 | 揚げ物の調理法全般を指すこともある | 竜田川の紅葉の色に由来するという説が有名 |
近年では、唐揚げでも下味をつけたり、片栗粉を使ったりすることが多いため、明確な区別がつきにくくなっているのが実情です。
しかし、伝統的な竜田揚げは、しっかりとした下味と片栗粉の衣による独特の風味と食感が特徴と言えると思います。
なぜ 唐揚げというの

「唐揚げ」という名前の由来には、いくつかの説がありますが、最も有力なのは以下の2つです。
- 「唐(とう)」からの渡来:
- 奈良時代に中国(当時の唐)から遣唐使を通じて「揚げる」という調理技術が日本に伝わったため、その「唐」の字を取って「唐揚げ」と呼んだという説です。
- 江戸時代初期に日本に伝わった中国の普茶料理(精進料理の一種)にも「唐揚げ」という名前の料理があり、これは豆腐などを油で揚げたものでした。この「唐揚げ」が、中国風の揚げ物全般を指す言葉として広まったと考えられています。
- 日本では、海外から伝わったものや珍しいものに「唐」の字を冠することがよくありました。(例:唐辛子、唐黍(トウモロコシ)など)
- 「空(から)」で揚げる:
- もう一つの説は、「空(から)」で「空揚げ」と書き、食材に衣をつけずにそのまま油で揚げる「素揚げ」を指す言葉だった、というものです。
- 昔は、食材に何も味付けや衣をつけずに揚げることを「から揚げ」と呼んでいた時期があったようです。
これらの説から、現代の「唐揚げ」は、中国から伝わった揚げる技術や、もともと「素揚げ」を指す言葉が変化して、現在のような味付けされた揚げ物を指すようになったと考えられます。
現在では、「唐揚げ」と「空揚げ」はどちらも使われますが、日本唐揚協会などでは、歴史的な経緯から「唐揚げ」の表記を推奨しているようです。
なぜ 竜田揚げって言うの
「竜田揚げ」という名前の由来には、いくつかの説がありますが、最も有力で、情緒あふれる説は、紅葉の名所として有名な奈良県の「竜田川(たつたがわ)」に由来するというものです。
この説によると、竜田揚げは、
- 醤油ベースの下味によって揚げ色が赤褐色になること
- 片栗粉をまぶして揚げることで、揚げ上がりに白い粉(衣)がところどころに残ること
これらの様子が、竜田川に舞い散る紅葉が、水面に錦のように美しく浮かんでいる情景に見立てられた、と言われています。
竜田川は、平安時代の歌人である在原業平(ありわらのなりひら)の「ちはやぶる 神代もきかず 竜田川 からくれなゐに 水くくるとは」や、能因法師の「嵐吹く 三室の山の もみぢ葉は 竜田の川の 錦なりけり」など、数々の和歌にも詠まれてきた紅葉の名所です。
日本の伝統的な料理名には、自然の風景や季節の移ろいを表現したものが多く、「竜田揚げ」もその一つと考えると、非常に風情があるのではないでしょうか。
他に、旧日本海軍の巡洋艦「龍田」の艦内で考案された、という説も一部で語られることがありますが、上記の竜田川の紅葉に由来するという説が広く知られています。
唐揚げと竜田揚げ 昔からあるのどっち
結論から言うと、唐揚げの方が古くから存在します。
「唐揚げ」という言葉は、江戸時代初期に中国から伝わった普茶料理(ふちゃりょうり)に由来すると言われています。
当時の「唐揚げ」は、現在の鶏肉の唐揚げとは異なり、豆腐を油で揚げて醤油と酒で煮たものでした。
しかし、「油で揚げたもの」という意味合いで「唐揚げ」という言葉が使われていたことは確かなようです。
一方、現在の「鶏の唐揚げ」に近い形で外食メニューに登場したのは、昭和7年頃に東京の「三笠会館」が「若鶏の唐揚げ」を考案したのが最初とされています。
これが一般に広く普及したのは戦後のことです。
対して「竜田揚げ」は、その正確な発祥ははっきりしていません。
しかし、文献上は1924年の『経済的食物調理秘訣』に「立田揚」の記述が見られるため、少なくとも大正時代には存在していたと考えられます。
また、鯨の竜田揚げが戦後の学校給食で広く親しまれたことで、その名が全国的に知られるようになりました。
したがって、広義の「唐揚げ」(油で揚げる調理法)は江戸時代初期から存在し、現在の「鶏の唐揚げ」も昭和初期には登場しています。
一方の「竜田揚げ」は、より新しい概念の揚げ物と言えると感じました。
![]()
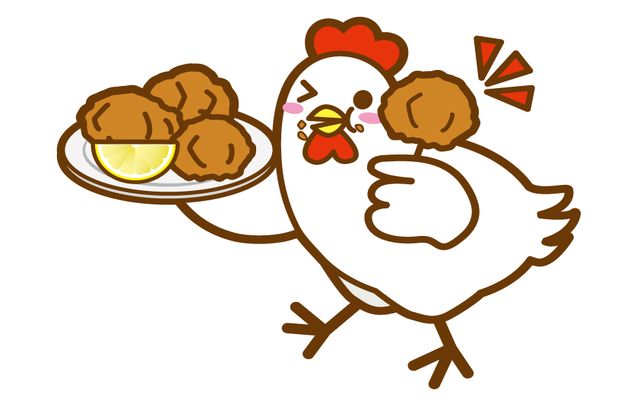


コメント