昔使われていた差別用語は、時代や状況によって様々です。
主なものとしては、特定の職業や身分、民族、身体的特徴などに基づくものが挙げられます。
人の心を傷つける言葉 差別用語

身分・職業に関する差別用語:
- 穢多(えた)、非人(ひにん): 江戸時代に存在した被差別身分に対する蔑称です。
- 特殊部落(とくしゅぶらく): 明治時代以降、被差別部落を指す言葉として用いられましたが、差別的なニュアンスを含むため現在では避けられています。
- 部落民(ぶらくみん): 被差別部落出身の人々を指す言葉ですが、文脈によっては差別的に響くことがあります。現在では「被差別部落出身者」や「部落問題」といった言葉が用いられる傾向があります。
民族・外国人に関する差別用語:
- 外国人(がいこくじん): 単に外国籍の人を指す言葉ですが、一部には差別的な意図を持って使われることがあります。より丁寧な表現としては「外国籍の方」などが用いられます。
- 三国人(さんごくじん): 第二次世界大戦後、在日朝鮮・台湾籍の人々を指して使われた蔑称です。
- 特定の民族や国籍に対する侮蔑的な表現は多数存在します。
身体的特徴に関する差別用語:
- 特定の身体的特徴を持つ人々を揶揄したり、見下したりする言葉は、障がいのある方やそうでない方に対しても存在します。
これらの差別用語は、社会の認識の変化や人権意識の高まりとともに、使用が避けられるようになっています。しかし、残念ながら現代においても、形を変えて差別的な言動や表現が残っている場合があります。
重要なのは、過去の差別用語を知り、その背景にある差別意識を理解することで、現代社会における差別をなくしていくことです。言葉の持つ力は大きく、何気ない言葉が誰かを深く傷つける可能性があることを常に意識する必要があります。
昔使われていた身体的特徴に関する差別用語は、非常に多く存在し、時代や状況によっても様々です。以下にいくつかの例を挙げますが、これらの言葉は現在では不適切であり、使用すべきではありません。
障がいに関する差別用語:

- めくら: 視覚障がいのある人を指す蔑称。
- つんぼ: 聴覚障がいのある人を指す蔑称。
- おし: 言語障がいのある人を指す蔑称。
- どもり: 吃音のある人を指す蔑称。
- びっこ: 足が不自由な人を指す蔑称。
- 片輪(かたわ): 身体の一部に障がいのある人を指す蔑称。
- きちがい: 精神障がいのある人を指す蔑称。(現在では「精神疾患のある方」などと表現します)
- てんかん: てんかんのある人を指す蔑称。
- 白痴(はくち)、阿呆(あほう)、 知恵遅れ: 知的障がいのある人を指す蔑称。(現在では「知的障がいのある方」などと表現します)
外見に関する差別用語:
- チビ: 背の低い人を指す蔑称。
- デブ: 体格の大きい人を指す蔑称。
- ハゲ: 頭髪の薄い人を指す蔑称。
- 特定の顔のパーツや肌の色などを揶揄する言葉も存在します。
これらの言葉は、令和の時代でもよく耳にしますしお笑い芸人では自虐ネタに活用さえしています。
その他:
- 病気や体質などに関する差別的な表現も存在します。
さいごに
これらの言葉は、相手を傷つけ、尊厳を損なうものです。
社会全体で差別的な表現をなくし、互いを尊重する言葉遣いを心がけることが重要です。
現在では、これらの差別用語に代わる、より適切な表現が用いられています。
例えば、障がいのある方を指す場合は、「視覚に障がいのある方」「聴覚に障がいのある方」のように、具体的な状況や状態を表す言葉を使うことが推奨されます。
差別用語の歴史を知ることは、過去の差別を認識し、現代社会における差別をなくすための第一歩となります。
私たちは、言葉の持つ力と影響力を理解し、より 健全な社会を目指していく必要があるのかもしれませんね。

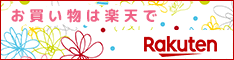


コメント