実は、お盆の期間は地域によって大きく異なります。
お盆っていつからいつまで?
1. 一般的なお盆(月遅れ盆・旧盆)
- 期間: 8月13日~16日頃
- 地域: 一部の地域を除く全国
- 由来: 明治時代の改暦(新暦への移行)の際、農作業が忙しい時期を避けるため、旧暦のお盆に近い8月に行うようになったとされています。この時期は「旧盆」とも呼ばれます。
2. 7月のお盆(新盆)
- 期間: 7月13日~16日頃
- 地域: 東京都、神奈川県、静岡県、石川県の一部地域など
- 由来: 新暦に移行する際、旧暦の7月15日をそのまま新暦の7月15日に当てはめたものです。
3. その他
- 沖縄地方: 旧暦に基づいてお盆を行うため、毎年お盆の時期が異なります。(2025年は9月4日~6日頃)
ご自身の住んでいる地域や、帰省先の地域のお盆の時期を確認しておくと良いでしょう。
お盆は国民の祝日ではありませんが、多くの企業が8月13日~16日頃を「お盆休み」とすることが一般的だそうです。
お盆とお彼岸って何が違うの?

お盆とお彼岸は、どちらもご先祖様を供養する大切な行事なのに違いがよく分かりませんが、その意味合いや時期、期間には違いがありました。
1. お盆
- 意味: あの世からこの世に帰ってくるご先祖様の霊をお迎えし、供養する期間です。
- 時期: 一般的には8月13日から16日頃(地域によっては7月)に行われます。
- 主な行事: 迎え火や送り火を焚いてご先祖様の霊をお迎え・お見送りしたり、きゅうりやナスで精霊馬を作ったり、盆提灯を飾ったりします。ご先祖様が家に帰ってくるため、家族や親戚が集まって一緒におもてなしをするのが特徴です。
2. お彼岸
- 意味: 煩悩に満ちたこの世(此岸)から、悟りの世界であるあの世(彼岸)へ到達するための仏教の修行期間です。
- 時期: 春分の日と秋分の日を「中日」として、その前後3日間を合わせた合計7日間、年に2回行われます。
- 主な行事: お墓参りや仏壇の掃除をしてご先祖様を供養します。お彼岸は、ご先祖様が帰ってくるのではなく、この世とあの世がもっとも通じやすくなる期間と考えられているため、こちらからお墓に出向いて供養をします。また、春には「ぼた餅」、秋には「おはぎ」をお供えする風習があります。
| お盆 | お彼岸 | |
|---|---|---|
| 意味 | ご先祖様の霊を家に迎える | あの世へ到達するための修行期間 |
| 時期 | 8月(7月の地域もある) | 春分の日・秋分の日を中心とした期間 |
| 期間 | 4日間ほど | 各7日間(年2回) |
| 主な行事 | 迎え火・送り火、精霊馬、盆提灯 | お墓参り、仏壇の掃除、ぼた餅・おはぎのお供え |
春と 秋のお彼岸の違いって何?
春のお彼岸と秋のお彼岸と年に二回あります。
季節以外の違いってあるのでしょうか?
どちらもご先祖様を供養する仏教の行事であることに変わりはありませんが、主にお供え物と季節的な意味合いに違いがありました。
1. お供え物の違い
最もよく知られている違いは、お供えする餅菓子の名前です。
- 春のお彼岸: 「ぼた餅」
- 春に咲く「牡丹(ぼたん)」の花にちなんで名付けられました。
- 昔は、春に使う小豆は収穫から時間が経って皮が固くなっていたため、皮を取り除いた「こしあん」を使うことが多かったとされています。
- 秋のお彼岸: 「おはぎ」
- 秋に咲く「萩(はぎ)」の花にちなんで名付けられました。
- 秋は小豆の収穫時期にあたるため、皮が柔らかく、風味豊かな「粒あん」を使うことが多かったとされています。
現在では、どちらの時期も粒あんやこしあんの区別なく作られていますが、昔からの風習として名前を使い分けることが一般的です。
2. 季節的な意味合いの違い
春と秋のお彼岸は、それぞれの季節の自然の恵みや移り変わりと結びついています。
- 春のお彼岸:
- 「春分の日」は「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」とされています。
- 冬の寒さが和らぎ、新しい生命が芽吹く季節であることから、豊作を祈願する意味合いも含まれています。
- 秋のお彼岸:
- 「秋分の日」は「祖先をうやまい、亡くなった人々をしのぶ日」とされています。
- 稲の収穫時期と重なることから、ご先祖様や自然の恵みに感謝する意味合いがより強いとされています。
このように、春と秋のお彼岸は、同じご先祖様供養の行事でありながら、その時期ならではの自然や風土に根ざした意味合いが込められているそうです。
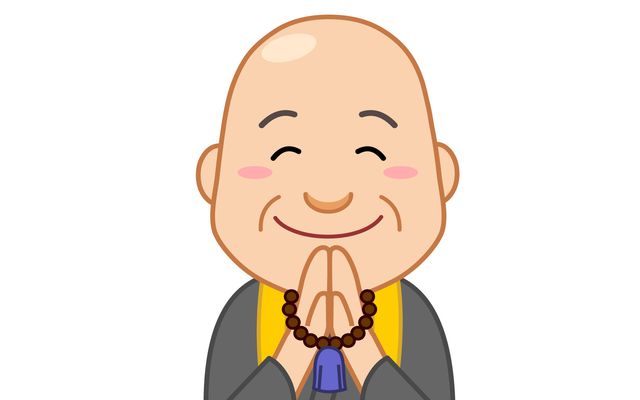


コメント