松下幸之助、100年の教え「人間、偉大なり」
2018年3月に創業100年を迎えるパナソニック。その創業者、松下幸之助の教えは経営哲学にとどまらず、人間の生き方にも及ぶ。同氏の元で数々の言葉に接してきた筆者が、「経営の神様」がどんな哲学で日本を代表するグローバル企業を育て上げたのかを読み解く。
悩みに悩んだ少年時代
松下幸之助(1894〜1989)は、「哲学者」であった。「哲学とは、人間について、自ら考え抜き、その本質を追求し、明確にすること」であるとするならば、まさにギリシャの哲学者たちのように、松下幸之助もまた、人間について、自ら考え抜き、本質を追究し、彼なりに明確にした「哲学者」だと言えるだろう。
その生涯は、「人間についての考察の日々」であった。なぜそのように人間について深く考えるようになったのか。その理由は、彼の「家族の死」にあったのではないかと思う。
松下家は両親、姉兄7人と本人の10人家族であった。彼の家はその村である程度の名家であったが、彼が4歳の時、父親はコメ相場に大失敗して破産する。もちろん、所有していた全ての田畑も家も手放さざるを得なかった。そのため家族は離散し、それぞれに自分で食べていかなければならなくなる。彼も9歳で故郷である和歌山の地を離れ、商売の本場である大阪の船場(せんば)に就職をせざるを得なかった。
そこで、商売人の心得や商売の仕方、さらには人情などを学ぶことになるが、それだけであれば、松下幸之助が「哲学者」になることはなかった。
しかし、彼が10代の、10年間で、1人の姉を除いて両親、姉兄が次々に結核で亡くなっていった。1年で2人の葬式を出すということも2回あった。そういう家族の毎年のような死に直面して、当然、「死とは何か」「生とは何か」「人生とは何か」「人間とは何か」を真剣に、時に深刻に考えたであろうことは想像に難くない。
10代の小学校を中退した少年にとって、その問いは自問自答する以外になかった。家族の死による「人間とは何か」の命題は、トラウマ(心的外傷)のように彼の脳裏から離れることはなかったと思う。
他者に対する責任と尊敬
そして、長い長い思考の末にたどり着いた彼なりの結論は、「人間とは偉大な存在」「人間は、誰もがいわば、ダイヤモンドを持っている存在」ということ。彼らしい表現で言えば「人間は万物の王者」ということであった。詳細については、彼の書いた『人間を考える-新しい人間観の提唱』(PHP研究所、1972年)にまとめられている。
この結論について、「傲岸(ごうがん)」「不遜」という批判は当たらない。彼は同時に、「そのために王者としてふさわしい責任を果たせ」と主張しているからである。責任は役割、立場に比例する。もし人間が小さな存在、罪深い存在、猿と同じ立ち位置であると主張する学者、宗教家がいるとすれば、人間に「大きな責任」を求め、追及することはできない。大統領も人間、国民も人間、ゆえに大統領の責任は、国民と同程度でいいと主張する者はいない。
松下幸之助は、人間お互いがつまらない存在と考えるところから戦争が起こる、殺人も弱者いじめも人間が猿同様の存在と思うところから起こるのだと主張する。そして、「侵すべからざる尊厳を有した存在、それが人間」と考えるならば、そこに他者への責任と尊敬の念が生まれ、悲劇は回避されると考えた。今日の人間の悲劇は、人間を「罪深い存在」「小さな存在」という通念に呪縛され、それゆえ、小さな責任しか追及できないところに起因しているということである。
彼は自分の哲学を問われたとき、「一言で言えば、人間大事ということに尽きる」と応えている。この言葉は、彼の人間観の極めて重要なキーワードと言えるだろう。
相手を限りなく大事と考え、お互いに差別区別することなく愛する。そして、責任をもって振る舞う。もちろん人間が大事であるがゆえに、よって立つ万物に対してもそれぞれを尊重し、許す限りにおいて、それぞれの本来の姿を維持する役割を果たさなければならないということである。
人間大事の経営哲学
松下幸之助の経営者としての人生は、23歳の時(1918年)に自分の考案した改良ソケットをつくる事業から始まった。これが現在のPanasonic(旧・松下電器)の創業となるが、人間大事の哲学を経営に取り入れながら、事業を進めていくことになる。
従って、彼の経営は「人間大事の経営」「人間偉大の経営」と言える。だからこそ偉大なる存在として従業員を大事にした。偉大なる存在としての顧客を大事にした。顧客でない人たちもまた、偉大なる存在として大事にした。多くの国民、さらには全人類をも大事にした。彼にとっては、全ての人たちが「偉大な存在」「大事な存在」であった。
彼が産業人の使命として、「いいものを、安く、たくさん」つくり、提供すると考えていたことは、有名である。多くの人々は、利益が上がるから、あるいは商売が、経営がうまくいくことが産業人の使命だと思っている。
しかし、松下幸之助はそうは考えなかった、利益を第一に考えて経営をし、商売をすれば、確かに利益は上がる。経営はうまくいく。だが、それゆえに「いいものを、安く、たくさん」と言っているのではない。
それは「いいものを提供しなければ、偉大なる存在である人々に、あるいは顧客に申し訳ない」という考えからきている。「安く」ということに関しても、原価を割って安くではない。さりとて、暴利をむさぼるような価格ではない。まさに「お客よし、自社よし、社会よし」という三方よしの適正価格。そういう価格でなければ、「ダイヤモンドの存在たる人間、顧客に無礼である」という考えだ。「たくさん」も同じこと。過不足なく適量でなければ、適正価格はおぼつかない。まして不正を行う経営は、人間悪、社会悪ということになる。このように、松下幸之助の経営は、「人間は王者」「人間は大事な存在」という哲学を根底にしている。
社員に対しても、安易な人員整理、解雇をすることはせず、彼らを大事にした。それゆえに、そうした事態を避けるべく知恵を出した。奇妙に思うかもしれないが、彼の経営哲学では、利益を上げるということは第二義的であった。何より従業員の幸せ、満足を達成することが優先された。従業員を常に励まし、謙虚な誇りを持たせ、感動を与え、そして従業員に感謝し続けた。それは「人間は偉大な存在」「人間大事」の哲学ゆえである。その結果が、彼に予想以上の経営的な成果をもたらすこととなった。
起業した時、まさに「ゼロからの出発」であったが、94歳で亡くなるまでの70年間の経営者としての成果は、7兆円の企業を築き上げたことであった。こうした偉業は、彼の経営哲学によるものであったと言える。
凡人たる自分を生かす道を考えて
松下幸之助は、常に「自分は凡人である」と認識していた。学校も出ていない。病弱であった。家族もいない。帰る故郷もない。そういう自分自身を客観的に眺めて、とても優れているとは思えなかったのだろう。誰と接しても、自分よりはるかに物知りで、賢明だと感じた。
しかし、松下幸之助の素晴らしいのは、劣等感を持ち、みずからを卑下し卑屈にならなかったことだ。現実を直視して、では、どういう対応をしたら、凡人たる自分を生かし、自分の人生を充実したものにすることができるかを考え、実行した「非凡さ」を備えていた。
彼が、「偉大なる存在である人間」の、周囲の人たちの意見、話を聞き、自らを高めることができたのは、自分を「凡人」と堂々と自認し公言することに吝(やぶさ)かではなかったからだ。
「凡人の意識」を持ち続け、「人間、偉大なり」という人間観を構築し、具体的に「人間大事」という考えから常に全てを発想したこと。こうした彼の哲学によって、経営者として、また人間として、結果的には、彼自身も予想しなかったほどの大きな成果を勝ち得たと言っても間違いない。
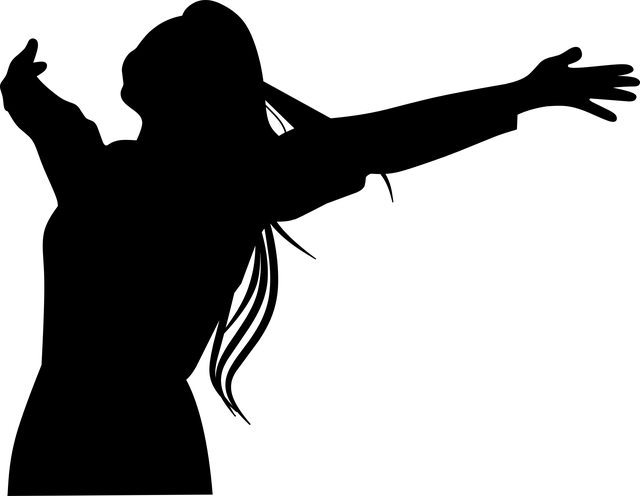

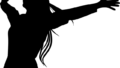
コメント